岐阜県高山市で年2回開催される高山祭は、古い町並みと豪華絢爛な屋台、からくり人形や祭行列などが織りなす日本三大美祭のひとつ。2025年も「春の山王祭」は4月14・15日、「秋の八幡祭」は10月9・10日に予定され、例年、国内外から多くの観光客を集めています。
伝統文化の保存と職人の技が随所に光る屋台、提灯が灯る夜祭、御巡幸や屋台曳き揃え・屋台曳き廻しなど多彩な行事が続きます。
この記事では、秋の高山祭の概要や歴史から初めての人でも効率よく楽しめる見どころや屋台グルメ、アクセス方法・駐車場・交通規制情報、混雑のタイミング、周辺観光スポットを網羅してお届け。訪れる前に押さえておきたいポイントが一目で分かるガイドとなっているので、ぜひご活用ください。
イベント概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| イベント名 | 高山祭(春の山王祭・秋の八幡祭) |
| 開催日時 | 春:2025年4月14日(月)・15日(火) 秋:2025年10月9日(木)・10日(金) |
| 開催場所 | 春:日枝神社および高山市中心部(城山・安川通りほか) 秋:櫻山八幡宮および高山市中心部(桜町・安川通り北側他) |
| 例年来場者数 | 春:約19万人 秋:約25万人 |
| 有料観覧席・入場料の有無 | 屋台会館など展示施設は有料 |
| お問い合わせ先 | 高山市観光課 飛騨・高山観光コンベンション協会 |
| 公式サイト | 春の高山祭公式ページ(飛騨高山旅ガイド) 秋の高山祭公式ページ(飛騨高山旅ガイド) |
| 周辺マップ | 春の会場:日枝神社(その他、高山市中心部古い町並み含む)
秋の会場:櫻山八幡宮(その他、高山市中心部古い町並み含む) |
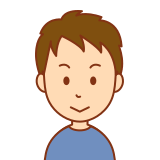
春・秋ともに2日間の開催で、観光シーズンとしては特に混雑する時期です。交通手段や宿泊の手配はお早めに、見学時間や観覧場所を計画的に抑えておくことがよりスムーズな移動に繋がります。
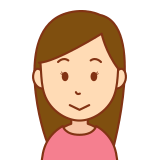
雨天時の行事中止や変更も随時公式サイトを確認しておくと安心でしょう。
高山祭とは?
歴史について
高山祭は、春の「山王祭(さんのうまつり)」と秋の「八幡祭(はちまんまつり)」を総称する祭りで、岐阜県高山市の例祭として江戸時代以前から続いています。
山王祭は、慶安5年(1652年)の記録に3年ごとに何らかの祭礼があったとの記述があり、のちに毎年行われるようになった祭礼です。屋台が加わったのは宝暦年間以降とされます。
由来について
「山王祭」は日枝神社の例祭で、氏子地域の守護と春の訪れを祝う意味があります。屋台(山車)を曳くことで地域を巡り、神様を迎える行列や祈願を行います。
秋の高山祭(八幡祭)見どころ
豪華絢爛な屋台(山車)
春は12台、秋は11台の屋台が登場。彫刻、見送り幕、刺繍、色彩など細部にまで技が光る芸術品のような屋台です。
からくり奉納
三番叟・石橋台・龍神台など屋台に備えられたからくり人形による演技。精巧な動きや表情が見どころです。
御巡幸(祭行列)と獅子舞・闘鶏楽
伝統衣装をまとった行列が町を練り歩く様子。お囃子・雅楽・獅子舞などが加わり、祭りの雰囲気を盛り上げます。
夜祭(宵祭)と提灯の灯り
夜になると屋台に提灯が灯され、昼とは異なる幻想的で艶やかな風景が広がります。
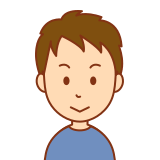
春の祭典は桜・新緑、暖かい気候・明るい色調と賑やかさを、今回の秋の祭典は初歩の紅葉・涼しい空気・少し落ち着いた趣があり、気候・景観共に異なる趣を楽しめるのがいいですね。
イベントスケジュール
以下、秋の高山祭(2025年10月9日・10日) の主なプログラムを日ごと表にまとめました。
| 日付 | 時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月9日(木) | 9:00~17:00頃 | 屋台曳き揃え |
| 12:00~12:20 ごろ | からくり奉納(布袋台など) | |
| 13:20~15:30 | 御神幸(祭行列) | |
| 13:30~16:00 | 屋台曳き廻し | |
| 18:15~20:30 | 宵祭 | |
| 10月10日(金) | 8:30~12:00 | 御神幸(祭行列) |
| 9:00~16:00 | 屋台曳き揃え | |
| 11:00~11:20 | からくり奉納 | |
| 13:00~13:20 | からくり奉納 | |
| 13:30~16:00 | 御神幸(祭行列) |
アクセス方法
電車の場合
バスの場合
車の場合
中部縦貫自動車道の高山ICから市内へアクセス可能。車での来訪は駐車場の確保・混雑・交通規制を考慮する必要があります。
会場周辺では交通規制が敷かれるため、車で近づけない場所もあります。できるだけ公共交通機関の利用が推奨されています。
周辺駐車場
-
臨時駐車場:秋の高山祭には無料の臨時駐車場が用意されることがあります。
-
民間・コインパーキング:市街地には所々コインパーキングあり。ただし祭期間中は満車になることが非常に多い。できれば宿泊施設併設駐車場や少し離れた駐車場を事前予約するのが望ましい。
-
屋台会館付近:高山祭屋台会館には50台程度の駐車スペース(普通車)があります。
屋台やキッチンカーの出店について
-
屋台(露店):祭期間中、本町通り・安川通り周辺および御旅所付近などに多数出店。食べ物・飲み物・土産物等。出店数は公式には記載が定かでないが、多数あり混雑が予想される。
-
営業時間:日中の祭行事の時間帯に合わせて開くことが多く、夜祭の時間まで営業する露店もあれば、夜遅くなると閉まる店もあり。春の高山祭では14日夜に夜祭あり。
-
グルメ情報の例:飛騨牛料理、朴葉味噌、みたらし団子等、地元の食材を使った郷土料理が人気。混雑を避けるため開店直後またはピーク時間を外して巡るのが良い。
観覧場所
-
陣屋前交差点:屋台曳き揃えやからくり奉納のメインステージ。正面から迫力ある光景を撮影・観覧できるが、混雑が激しい。
-
安川通り・町並み散策エリア:少し距離を取り、屋台全体のシルエットや提灯が灯った夜の雰囲気を楽しむならこのあたりが穴場。
-
屋台会館:屋台が常設展示されており、祭の時間以外・雨天時にもじっくり観覧できる。静かに屋台を眺めたい人におすすめ。
周辺観光施設
-
高山祭屋台会館(桜町178) — 実物の屋台展示施設。祭の屋台を間近で見ることが可能。
-
高山陣屋 — 江戸時代の代官所跡。町並みとともに歴史を感じる施設。
-
古い町並(三町) — 出格子の町家、軒下の用水、伝統的な店構えなど。散策に最適。
-
日下部民藝館 — 伝統工芸品や民藝の展示。祭の装飾技術を別視点で楽しめる。
-
宮地家住宅・吉島家住宅など町家建築群 — 高山市には国指定・市指定の町家建築が点在し、祭の合間の散策に風情あり。
過去の祭りの様子について
-
昨年の様子:春の高山祭では、悪天候により一部行事(屋台曳き揃えやからくり奉納)が中止または屋台蔵での観覧となったケースあり。
-
混雑具合:祭開催期間中は市内中心部が早朝から混雑し始め、午後からピーク。夜祭時には人で通行が困難な通りも。宿泊施設・飲食店とも混み、待ち時間が長くなることも。ワンシーズンでの来場者数は春・秋で合計40万人を超える年もあり。
高山祭を楽しむコツ
-
公式スケジュールを事前に確認:雨天時の行事変更有。特に「からくり奉納」「屋台曳き廻し」など時間が決まっているものは時間を逃さないように。
-
観覧場所の確保は早めに:人気のポイント(陣屋前交差点、屋台曳き揃え場など)は少し早く行っていい場所を取るのが◎。
-
服装・持ち物に工夫を:歩きやすい靴、水分・帽子・日焼け止め、夜用の上着など。
-
食事は時間帯をずらす:昼食・夕食はピーク時間を避けて、地元の食堂や郊外を利用するのも手。
-
宿泊はできれば市中心部または会場近くを早めに手配:祭当日は満室になることが多いため。
-
雨対策を忘れずに:傘やレインコート、滑りにくい靴など備えておくと安心。
まとめ
高山祭は、春の山王祭・秋の八幡祭を通して、日本の伝統・美意識・地域文化を体験できる特別なイベントです。屋台の豪華さ・からくり奉納・祭行列・夜祭など、多彩な行事が待っています。
初めて訪れる人は、スケジュール・アクセス・駐車場などを前もって調べ、見どころを絞って行動することで、時間を有効に使えるでしょう。混雑前の時間帯や夜の雰囲気を狙う、観覧場所を工夫するなどで、ゆったり楽しむのもいいですね。また、屋台会館など展示施設を活用すれば、祭本番以外の時間も文化・工芸も見られます。
「見る」だけでなく、音、匂い、人々の掛け声、灯りの揺らめきなど五感で感じてこそ記憶に残る体験となるはずです。高山祭を思い切り楽しんで下さい。

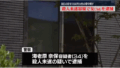
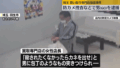
コメント